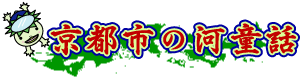「志古淵さん」と河童
左京区の久多に「志古淵さん」という水神様が祀られている。
新井清は『あしなか』第四十二号(昭和二十九年八月刊)に、「久多のガワ太郎」と題して、およそ次のような話を寄せている。
志古淵さんには、七人の男の子があり、時々、この子供たちを連れて、川下りをしていた。
初めのうちは、一人ずつ丸木に乗せて川を下っていたが、それでは面倒なので、そのうちに、丸木をくくり合わせて筏を作り、みんないっしょに乗れるようにした。
ある日、いつものように子供たちと筏を流していると、新畑川との合流点である川合の下流付近で、筏の先頭に乗って竿を握っていた長男の姿がフッと消えてしまった。
志古淵さんは、「これは、ガワタロ−の仕業に違いない」とにらんで、筏を解き、それで川に堰をし、下流の水を干してしまった。
すると、川の中に突き出ている大きな岩の下で、ガワタロ−が、長男の乳のあたりをしっかりと抱きかかえて、うずくまっているのが見えた。
志古淵さんが「子供を返せ」というと、ガワタロ−は「一度捕らえたものは返さない」というので、「年に三人だけ人の子をやるから、その子を返せ」というと、ガワタロ−はしぶしぶ承知した。
その時、志古淵さんは、今後、志古淵さんと同じような簑笠をつけ、ガマ(蒲)のハバキ(脚絆)を巻き、コブシの木の竿を持った筏乗りには手を出さないことをガワタロ−に約束させた。
この時、こういう取り決めがなされたので、その後も、安曇川筋では年に三人の水死人が出るが、志古淵さんと同じ姿をした筏乗りは無事だという。
なお、「志古淵神社」の古名は「思子淵神社」で、祭神は「斎部の神様」とも「筏の神様」ともいわれている。
また、志古淵さんの長男がガワタロ−に引き込まれた所にある大きな岩は「乳鋏み岩」と呼ばれている。
「志古淵さん」と河童
久多の「志古淵神社」の由来について、『京都・久多 ー女性がつづる山里の暮らし』(久多木の実会編 ナカニシヤ出版
平成五年)の中で、上野佐太郎は「筏乗りの神様、志古淵さん」と題して、およそ次のような話を書いている。
昔、久多庄に「志古淵さん」という筏乗りの名人がいた。
ある日、志古淵さんは男の子を筏に乗せて、いつものように久多川を下り、葛川の奥山という難所に差し掛かった。
ふと後ろを振り向くと、乗っているはずの子供の姿が見当たらないので、志古淵さんは筏を横にして、川をせき止め、あちこち探したところ、川下の大きな岩のウロ(穴)にガワラが脇に子供を抱えて潜んでいた。
ところが、そのガワラは、水をせき止められて大変弱っており、命乞いをしたので、志古淵さんは、今後、菅笠をかぶり、蓑をつけ、草鞋をはき、足にガマ(蒲)のハバキ(脚絆)を巻き、コブシ(辛夷)の竿を持った筏乗りには悪戯をしないことを約束させて助けてやった。
それ以後、筏乗りは晴雨にかかわらず、このような服装をするようになり、事故もなくなったので、志古淵さんは「筏乗りの神様」として敬われ、久多の氏神「志古淵神社」として祀られるようになった。
なお、ガワラが子供を抱えて潜んでいた所は「乳挟み」と呼ばれていたが、それが訛って、現在では「火挟み」という地名になっている。
「河原太郎」
本島知辰撰『月堂見聞集』は、元禄から享保末年に至る三都を主とした諸国の巷説を記したものであるが、その中に次のような記述がある。
河童に関する話は後半で、以下の引用文は、大正二年に國書刊行会から発行された『近世風俗見聞集第二』によるものである。
○五月下旬の比より、頂妙寺門前通東の方の新地に、月よと みの薬賣る家多し、此の処へ化け者出づ、或は女の首計出て、
人を見て消ゆ、或は女の小児を抱たる貌障子にうつる、或は やねの上を走る、右は昼夜を不分出づと云傳へて、諸人見物
夥し、所の者此れを禁ずれども止む事なし、然れども誰有て 見たるものなし、又五月廿六日日暮、三條大橋の下より真黒
なる者出づ、人ども大勢是を追ふ、彼のもの孫橋の下を通り て、東の方の茶屋の内へ入る、内外より此れを狩出せども、
遂に其の姿消て見えず、定て河原太郎、此間之海水にて、上 より流れ来る歟といへり
人の姿になった水の精
『今昔物語集』巻第二十七の「冷泉院水精成人形被捕語 第五」に次のような話が出ている。
昔、陽成院が住んでおられた御屋敷の跡地は、後に人家が建てられたが、南の方に池などが残っていた。
ある時、その人家に住んでいた人が、西の対屋の縁側で寝ていると、身の丈三尺ばかりの翁が現われて顔をなでるので、恐ろしくて空眠りをして横になっていると、翁はそっと立ちあがって、池の近くでかき消すように見えなくなった。
そこで、さては池に住む妖怪であろうかと思っていると、それ以後も夜な夜なその妖怪が出て来て顔をなでた。
そのことを人に話したところ、一人の腕自慢の男が「俺が、そいつを捕らえてやる」といって、その縁側に一人で苧縄を持って横になっていると、夜半過ぎに、顔に何やら冷たいものがさわった。
そこで、それを引っ捕らえ、苧縄でがんじがらめに縛り上げて、人を呼んだ。
皆が集まって来て、明りを灯して、よく見ると、身の丈三尺ほどで、上下とも浅黄色の衣を着けた小さな翁が、今にも死にそうな様子で縛り付けられ、目をしばたいており、何を聞いても答えない。
しばらくしてから、その翁が、か細い情けなそうな声で、「盥(たらい)に水を入れて持ってきてくださらぬか」というので、大きな盥に水を入れて前に置くと、翁は首を伸ばして盥に向かい、水に映る姿を見て、「我は水の精ぞ」といって、水の中に落ち込み、その姿は消え失せた。
翁は水になって溶け、消えてしまったのである。
人々はこれをみて、驚き怪しんだが、その盥の水をこぼさないように抱えて、池に入れた。
それ以後、翁が現われて、人の顔をなでることはなくなり、人々は「水の精が人になったのだ」と話し合ったという。
この話の舞台である「陽成院がお住まいになっておられた所」は、「二条大路の北、西洞院大路の西、大炊御門大路の南、油小路の東の地の二町」で、「院がお隠れになってからは、その地所の真ん中を東西に走る冷泉院小路を開いて北の町は人家」になっていた。
この物語が書かれた頃は、「河童」というものは、まだ考えられておらず、この翁になった「水の精」が河童の古い姿だといわれている。
河童の手を切り取った男
昔、山城の国伏見に、和田某という人がいた。
ある時、この人が淀川の堤を歩いていると、河童が出てきて、彼を水の中に引きれようとした。
彼は、それを踏みこたえ、河童の手を捕らえて、腰の刀で切り取ると、河童は叫び声を残して、川の中へ姿を消した。
彼は、その手を家へ持ち帰ったところ、その夜以後、七夜続けて、河童が来て、詫びを入れ、手を返してくれと頼んだが、彼はそれを聞き入れなかった。
そして、遂に切られた手を接ぐことができる期間が過ぎ、河童は大いに怨んで去っていった。
その河童の手は、今なお、和田家が所持しているということである。
これは、夾撞山人著『諸国便覧』(享和二年(一八○二年)刊)に出ている話である。
|